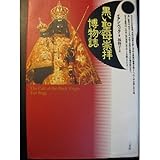9/15。
「芝大神宮」の参拝を終えて、すぐ近くにある「増上寺」を外すわけにはいかず。
◯こちら===>>>

いわゆる「芝大門」。



うーん、ちょっと遠い。
「三縁山 広度院 増上寺
浄土宗の七大本山の一つ。
三縁山広度院増上寺(さんえんざんこうどいんぞうじょうじ)が正式の呼称です。
開山は明徳四年(1393)、浄土宗第八祖 酉誉聖聡(ゆうよしょうそう)上人によって、江戸貝塚(現代の千代田区紀尾井町)の地に浄土宗正統根本念仏道場として創建され、文明二年(1470)には勅願所に任ぜられるなど、関東における浄土宗教学の殿堂として宗門の発展に大きく寄与してきました。
江戸時代初期、増上寺法主第十二世源誉存応(げんよそんのう)上人、後の「観智国師」が徳川家康公から深く帰依を受け、手厚い保護を受けました。
慶長三年(1598)に現在の地に移転し、徳川将軍家の菩提寺として、また関東十八壇林の筆頭として興隆し、浄土宗の統制機関となりました。
その規模は、寺領一万石余、二十数万坪の境内値、山内寺院四十八宇、学寮百数十軒、常時三千名の僧侶が修学する大寺院でした。
現代でも浄土宗大本山として格式を保ち、宗教活動のほか文化活動も幅広く行われ、建造物、古文書、経典など多数の重要文化財を所蔵しています。」
「七大本山」というのは、
◯総本山知恩院(京都)
を別として、
・増上寺(東京)
・光明寺(神奈川)
・善光寺大本願(長野)
・金戒光明寺(京都)
・知恩寺(京都)
・清浄華院(京都)
・善導寺(福岡)
を指しているそうです(Wikipediaより/大本山寺院一覧 - Wikipedia)
時々仏教で登場する「国師」という称号ですが、「コトバンク」によると、
1 奈良時代の僧の職名。大宝令により、諸国に置かれ、僧尼の監督、経典の講義、国家の祈祷(きとう)などに当たった。のちに講師(こうじ)と改称。
2 天皇に仏法を説き伝える法師。
3 禅宗をはじめ律宗・浄土宗の高僧に、朝廷から贈られた称号。「夢窓―」
だそうです。
うーむ……仏教の勉強は大変だなぁ……。
また、「壇林」というのはコトバンクによると、
《「栴檀林(せんだんりん)」の略。僧の集まりを栴檀の林にたとえたもの》
1 仏教の僧徒の学問修行の道場。室町末期から行われ、江戸時代の浄土宗の関東十八檀林は有名。
2 寺の異称。
3 「談林風」「談林派」の略。
(デジタル大辞泉より/檀林(ダンリン)とは - コトバンク)
ということです。
「栴檀」というインド原産の木は香木で、その薫りは心根を清浄にする働きがあるとして仏教で重宝されているようですが、その「栴檀」は実際には「白檀」のことだとか、何やらよくわからないので、この辺りで。
「三解脱門
慶長十六年(1611)に徳川家康公の助成により、江戸幕府大工頭・中村大和守正清によって建立され、元和八年(1622)に再建されました。
この門は、増上寺で唯一の江戸時代初期の面影を残す建造物で、重要文化財に指定されています。
三解脱門は、別名「三門」と呼ばれ、三つの煩悩「貪欲」「瞋恚」「愚痴」の三悪を解脱する悟りの境地を表しています。
建築様式は三戸楼門、入母屋造、朱漆塗。唐様を中心とした建物に、和様の勾欄などが加味され、見事な美しさを見せています。
その大きさは、間口十間余(約19メートル)奥行五間(約9メートル)高さ七丈(約21メートル)の二重建て構造。
「三つの煩悩「貪欲」「瞋恚」「愚痴」の三悪を解脱する悟りの境地を表しています。」というのは、もちろんそうに違いないのですが、どちらかというと「決意表明」というか、「願望」というか、そういった感じではないのかと。
「この門をくぐる以上は、三悪からの解脱をするぞー」とか、「三悪から解脱したい」とか。
もっとも、その時点で新たな煩悩が生まれていますので、悟りなんかできっこないと思いますが。
楼門にも仏像が安置されているのだ、ということを最近まで知りませんでした。

……下の文字が、「魚市場」としか読めないのですが、違うんでしょうか。

案内図。
広い。


「大殿」と東京タワー。

あ、手水場の瓦にも「葵」の御紋がありました。
公式HPによれば、
「水盤舎
もと清揚院殿霊廟(甲府宰相綱重公・三代家光公三男)の一部であり、明治時代の解体・昭和の空襲を逃れたものを、現在地に移築したもの。徳川将軍家霊廟建築を伝える貴重な遺構のひとつであります。」
「甲府宰相」ってどこかで聞いたな……と思ったら、
◯こちら===>>>
「根津神社」 - べにーのGinger Booker Club
↑の「根津神社」の記事で出てきました。
六代将軍の父親が、「甲府宰相」と呼ばれていた酒乱……ごほごほ……んでしたね。

「大殿
昭和四十九年(1974)、浄土宗開宗八百年の祈念事業として戦災に遭った本堂を再建しました。
(略)
本堂には、ご本尊の阿弥陀如来(室町期作)、両脇壇に高祖善導大師と宗祖法然上人の御像が祀られ、参拝される方々の厚い信仰をあつめています。」
焼けてしまったんですね……海も近いし、狙いやすそうですものね。

何かパースが狂っている気がしますが、これぞ東京という雰囲気も。
「大殿」の隣に「安国殿」という建物があります(撮影したかな……)。

「安国殿と黒本尊
この建物は徳川家康公の法号「安国院殿」からその名をとっています。「安国殿」とは元来家康公の尊像を祀る御霊屋を意味していましたが、戦後の復興に伴う境内堂宇整備の一環として、昭和四十九年(1947)当時の仮本堂をこの地に移転し、家康公の念持仏として有名な「黒本尊阿弥陀如来」を安置し「安国殿」と命名しました。
建物の老朽化に伴い、平成二十三年(2011)法然上人八百年御忌を記念し、念仏信仰の拠点として家康公が成し遂げた天下泰平の世(安らかな国づくり)を願い、新たに「安国殿」を建立しました。
「黒本尊」は当山の秘仏で、正月、五月、九月の各十五日、年三回行われる祈願会の時だけ御開帳されます。また両脇陣には、家康公肖像画、徳川家位牌、和宮像、聖徳太子像、仏舎利などが祀られており、庶民の信仰の中心として親しまれています。」
何と偶然にも、「「黒本尊」は当山の秘仏で、正月、五月、九月の各十五日、年三回行われる祈願会の時だけ御開帳されます。」という当日でした。
そのためか、参拝者も多く、幸運ではありましたが、開帳時間が午後2時ということで、断念。
しかし、「黒本尊」とはまた怪しげな……黒檀か何かで彫られているのでしょうか。
公式HPでは、
「恵心僧都の作と伝えられる秘仏黒本尊(阿弥陀如来)が祀られています。(御開帳・祈願会、正月・五月・九月の十五日)黒本尊は家康公が深く尊崇し、そのご加護により度重なる災難を除け、戦の勝利を得たという霊験あらたかな阿弥陀如来像で、勝運・厄除けの仏様として江戸時代以来、広く人々の尊崇をあつめています。」
と解説されています。
……阿弥陀如来が戦の加護をするのかどうか、については疑問がありますが。
他とは異なる、ということで力を発揮する(と信じられる)のは、今も昔も変わりありません。
そういえば西欧には、「黒い聖母」というものがあります。
◯こちら===>>>
若い頃に、
という本を読んだことがあるのですが、恐ろしいことに内容を全く覚えていません。
西欧の「黒い聖母」は、長い間蝋燭の煙などでいぶされたために黒くなってしまったものが多いようです。
日本の「黒い仏」も似たようなものなのかも知れません。
最初から黒漆塗、ということもありますが。
「黒い仏」といえば、
敬愛する故・殊能将之先生の怪作ミステリがあります(タイトルでネタ、というかオマージュ先がバレている、という辺りから怪作です)。
オチを書きそうになったので、軌道修正を。
「安国殿」の隣を通っていくと、

地蔵連続帯、そして、


「徳川家御霊廟」があります。



戦前、旧徳川将軍家霊廟は御霊屋(おたまや)とも呼ばれ、増上寺大殿の南北(左右)に建ち並んでいました。
墓所・本殿・拝殿を中心とした多くの施設からなり、当時の最高の技術が駆使された厳粛かつ壮麗な霊廟は、いずれも国宝に指定され拡張ある佇まいでした。
その後昭和二十年(1945)の空襲直撃で大半が焼失し、残った建物もその指定を解除されました。
正面の門は旧国宝で「鋳抜門」(いぬきもん)といわれ、文昭院殿霊廟(徳川家六代将軍家宣公)の宝塔前「中門」であったものを移築しました。
左右の扉は共に青銅製で五個ずつの葵紋を配し、両脇には昇り龍・下り龍が鋳抜かれ、その荘厳さは日光東照宮と並び評された往時の姿を今に伝える数少ない遺構です。
墓所には、二代秀忠公・六代家宣公・七代家継公・九代家重公・十二代家慶公・十四代家茂公の六人の将軍のほか、崇源院(二代秀忠公正室、家光公の実母、お江)、静寛院宮(十四代家茂公正室和宮)ら五人の正室、桂昌院(三代家光公側室、五代綱吉公実母)はじめ五人の側室、及び三代家光公第三子甲府宰相綱重公ほか歴代将軍の子女多数が埋葬されています。」
「鋳抜門」(いぬきもん)の制作方法がよくわかりませんが、彫刻ではなく鋳型でこの文様から龍までを抜いた、ということだとすると、「そりゃすげぇ」です。
ちなみに、裏側の葵の御紋が、

こちら。
絶対に、彫刻か、後から取り付けた方が早いのに、型をとったのか……職人すげぇ。
公式HPで案内されていますが、
増上寺御霊屋(徳川将軍家墓所)特別公開日
1月15日 正五九祈願会
4月2~8日 御忌大会・ふれあいフェア期間中
5月10日 景徳祭
5月15日 正五九祈願会
9月15日 正五九祈願会
10月2日 静寛院宮奉讃法要
10月9日・10日 みなと区民まつり(2009年は10月10日・11日)
【公開時間】 10時~16時
【料金】 無料
……ま、またしても幸運にも特別公開日だったとは。
こちらはありがたくお参りさせていただきましたが、参拝者も多く、あまり無造作に写真を撮るのもはばかられたので、遠景をパノラマで、ということにしておきました。

また、同じく公式HPでは、
「焼失した御霊屋郡はしばらくのあいだ荒廃にまかされていましたが、昭和三十三年(1958年)から文化財保護委員会が中心となり、詳細なる学術調査が行なわれ、のち土葬であった御遺体は桐ヶ谷にて荼毘に付され、南北に配していた墓所は一か所にまとめられ現在地に改葬されました。調査によれば細部では各将軍若干の違いあるも、埋葬の構造的には、まず地中かなり深い部分に頑丈な石室を設け御遺体を安置し、二枚の巨石をふたにして、その上に基檀と宝塔は安置されていたといわれます。」
とされています。
そうか、土葬だったんですね……そういえば最近、今上天皇陛下の「火葬を望む」という御発言がありましたが、天皇陵もお体が残っているんですよね……け、研究……。

将軍家墓所から戻る途中、振り返って地蔵連続帯を。

「大殿」向って右手に、「西向観音」があります。
由来がちょっとわかりません。

地蔵連続帯……ではなく、「千躰地蔵尊」。
地蔵に風車、という風景が何となくノスタルジックなのはなんなんでしょう……いや、連続の美というのが好きではあるんですが、よく考えると、結構ナンセンスですよね。


境内社として、「熊野三所大権現宮」があります。
「増上寺鎮守中最大なものとして、本殿拝殿あり、大きさ不明なれど東照宮に次ぐものなりと云う縁山志によれば、火災ありしも、明暦以来焼けたる事なし。
御神体は
熊野本宮大社 家津御子大神
以上の三御神体を祀り、故綿貫次郎翁のご指導により
「大本山増上寺熊野みこし講」を起こし、護持・奉賛しております。祭禮は毎年三月三日に古式にのっとり行なわれていましたが、近年は四月第三日曜日に定まる。
大本山増上寺熊野みこし講」
公式HPでは、
「元和十年(1624年)、当寺第十三世正誉廓山上人が熊野権現を増上寺鎮守として東北の鬼門に勧請したもの。『熊野』は「クマノ」・「ユヤ」と二通りの呼称がありますが、当山では「ユヤ」権現として親しまれています。」
とあります。

手水場。
「八咫烏」の紋が鮮やかですが……東日本大震災の影響でしょうか。

境内地は結構な広さで、尊崇されていることが窺えます。
観光客はいませんけれど。

「綿貫次郎」さんとみこし講40周年の記念碑。
「西暦1974年(昭和四十九年)
故綿貫次郎翁(通称おじいちゃん)は毎日増上寺安国殿に通い、奉仕活動を日課としていました。
増上寺の繁栄を願い、若者達の力でお手伝いをしようと関係のある神輿仲間に声をかけ、「熊野みこし講」を発足し行事に参加するようになりました。
増上寺の鬼門である熊野神社の社が老朽化したため、復興を願いみこし講の手づくりにて木の鳥居を建立。少しずつ改修を加え、現在の社殿及び玉垣が完成したのです。
江戸の町東京を愛する若者達の結集、これが「熊野みこし講」です。綿貫のおじいちゃんの言葉、「身をもって奉仕する気持」を受け継ぎ、末永く後世につないで行ける様、ここに四十周年を記念し石碑を建立いたします。
平成二十六年四月吉日 大本山増上寺 熊野みこし講」
失われる文化があり、受け継がれる文化があり、その分水嶺はどこにあるのか。
奇麗な言葉で言えば、「名も無き人達」の努力、なんでしょう。

一度境内から出て、地下鉄芝公園駅に向うと、右手に見えます門。
公式HPによれば、
御成門交差点付近の芝公園・みなと図書館・御成門小学校一帯にあった増上寺方丈の表門であった旧方丈門であります。三代将軍家光公の寄進・建立とされ、慶安年間(1648~1652)の建立とされております。明治時代に増上寺方丈に北海道開拓使の仮学校や海軍施設が置かれ、その後芝公園となったおり、鐘楼堂脇に移築したものを、昭和五十五年(1980年)に当山通用門として日比谷通り沿いに移築しました。
↑とのことです。
さて、
◯こちら===>>>
国立国会図書館デジタルコレクション - 江戸名所図会. 巻1
↑の102コマより、「増上寺」の記事があります(引用にあたって旧字をあらためた箇所あり/判読不能文字は■で置き換える)。
「三縁山増上寺
広度院と號。関東浄家の総本寺、十八檀林の冠首にして盛大の仏域たり。百一代後小松院の御願にして、開山は大蓮社酉誉上人、中興は普光観智国師なり。[割註]十八檀林は武總常野等に存在す。阿弥陀仏六八本願の中第十八を以て最勝とするに因み、御当家御称号松平氏の松や千歳を閲歴し能雪霜におかされず、又君子の操ありて、しかも太夫の封を受く、其字や木公に従ふ、細にわかつときは十八公なり、依て是を弥陀の十八願にかたどり給ひ、精舎十八区を建て永く栴檀林とし、多く英才を育して法運無窮の謀を設けたまひ、御子孫永く安からん事は霜雪の後松樹独栄茂する如くとの盛虜に従ひ、源家の御代を浄家の白旗流義により、千代万代までも守護し奉るべき旨表し給ふなりとぞ。以上浄宗護国篇、新著聞集等の意を採摘す。」
本堂本尊阿弥陀如来 [割註]恵心僧都の作にして、座像御長四尺ばかりあり、或云仏工運慶が作なりと。」
(略)
御経蔵 [割註]本堂の前左の方塀の中にあり、或人云、ここに納る所の一代蔵経は宋板にして、其先豆州修善寺にありて平政子の寄附なりとぞ。後彦坂九兵衛尉台命を奉じ当山にうつすとなり。菊岡沾凉云、昔は方丈にありしを、寛永九年照誉上人了学大和尚経蔵を創立したるとなり、今は官造に列す。」」
一旦休憩。
「細にわかつときは十八公なり」……「松」の地を分解するとこうなるなぁ、というのは昔思ったことがあります。
この手の漢字分解は日本人(というか漢字文化圏なら)は好きですよね。
「米」が「八十八」だったり。
……あれ、他に思い浮かばない……。
「経蔵」に関しては、公式HPでは、
「徳川幕府の助成により建立された経蔵は内部中央に八角形の輪蔵を配する、八間四面、土蔵造りの典型的な経蔵で、都の有形文化財に指定されています。中に収蔵されていた宋版、元版、高麗版の各大蔵経は、家康公が増上寺に寄進したもので、国の重要文化財に指定されています。(現在は後方の収蔵庫に移管)」
ということです(写真、取り忘れました)。
「開山堂 [割註]同所左にならぶ、当山開山以下塁世大僧正の肖像および霊牌等を置れたり。
開山酉誉上人、諱は聖聡、大蓮社と號す。 [割註]鎮西正統第八世の祖とす。」 貞治五年七月十日 [割註]千葉系図貞治二年六月三日とあり。」 北總の千葉に生る、乳は千葉陸奥守氏胤、母は新田氏なり、童名を徳寿丸と云。 [割註]一書に徳千代とあり。」 加冠して胤明と称す、出離の志深く釋典を慕ふ、九歳にして遂に同国千葉寺に入て落飾し、初て密教を学び、後冏公に投帰して浄宗に入、智道倍熾なり、其後武州豊島郡江戸貝塚の光明寺に住せらる。 [割註]今の増上寺是なり。江戸名勝志に云、増上寺の舊地は糀町一丁目越後やしきと云辺なりとあり。」 此寺始は真言瑜伽の道場なりしが、竟に光明寺を改て三縁山増上寺と號し、宗風をも転じて浄業の精舎とす。永享十二年庚申七月十八日寂す、歳六十五臘六十七。 [割註]東国高僧伝に応永二十四年に寂す、寿詳ならずとあり。」 中興開山、勅賜普光観智国師、諱は存應、字は慈昌、貞蓮社源誉上人と號す。 [割註]平山左衛門尉季重の後裔なり、伝燈系図に云、姓は由木又は金吾校尉源利重云々。」 天文十三年 [割註]護国篇十年に作る。」 武州由木の生る、始衣を片山の宝台寺に摳(※てへんに區/かいつくろ)ひ、十八歳感誉上人に帰して登壇受戒す、天資聡悟にして顕密の教を究む、上人歿後上簑に到て長伝寺を創し大に法席を開く、人呼で教海の義龍蓮苑の祥鳳といふ。天正十三年雲誉上人の会下にあり、同十七年八月璽書を伝承して増上寺第十二世となる。 [割註]当寺第十二世たり。」 同十八年天下安靖たるに逮んで大に大神君の眷顧を給ひ、屢営中に請せられて法要を聴受し給ひ、崇信他に異なり、竟に増上寺を修営せられ植福の地となし給へり。又後陽成帝師を宮内に徴して道を問給ふ、盛に浄教の深旨を陳ず、叡感ありて褒章を加へ新に宸翰を染給ひ、特に普光観智国師の號を賜ふ、時に慶長十五年七月十九日なり。元和六年師微恙を示す、嗣君大将軍親ら臨んで忝くも疾を問せ給ふ。十一月二日諸徒に遺誡し辞世の偈を書して曰く、仏話提撕心頭塵、末後一句但称仏、と筆を抛て端座合掌し仏號を唱へて化す、世寿七十有七僧臘六十。 [割註]護国篇世寿八十とあり、いづれか是なる事をしらず。」 門葉■々として学徒流に浴す、撰述する所、論義決択集、阿弥陀経直譚等大に世に行はる。 [割註]以上浄土高僧伝、浄宗護国篇、伝燈系図等に出つ。」
(略)
熊野三所権現祠 [割註]同所にあり。則当寺の鎮守にして護法の神と称す。」」
「開山堂」は焼失して、再建はされていないようです。
「熊野三所権現」の記事が少ないですね……。
ええと、さすが「増上寺」、『江戸名所図会』での扱いも破格で、記事の量も多いので、ひとまずここまで、続きは次回ということで。